木の花屋とは
*名前の由来について
木花咲耶姫の優しい心を大切に引き継いできた、この地域の人々の心を、後世まで伝えたいと思い、語り継がれてきた地元の民話から頂戴いたしました。千曲市さらしなには、月の名所として有名な姨捨山があります。松尾芭蕉も訪れたその大岩の横に長楽寺というお寺がありますが、この民話はそこに伝わる縁起でもあります。
*木の花姫のお話
大むかし、木花咲耶姫(コノハナサクヤヒメ)という心も姿も美しい姫がおりました。この姫に大山姫という心も姿もみにくい叔母がいました。
「めいの咲耶は、かがやくほど美しいのに、この私はなんとみにくいことか。」
大山姫は、自分の姿を水にうつしてはくやしがっていました。
「人は姿や顔の美しさより、心のやさしさが大切ではないでしょうか。」
と咲耶姫がいうと、
大山姫は
「たいそうえらぶった口のききようだこと、美しい咲耶に、みにくい私の心などわかるわけがありませぬ、ええええ、どうせ私は、顔のとおり、心もみにくうございますとも。」
とたいそうお腹だちになりました。
咲耶姫は、自分のまごころが通じないばかりか、いえばいうほど、大山姫がひねくれていくように思われ、どうしてよいのやらわからなくなりました。
大山姫はまた、
「みにくい者には、着飾るより楽しみがありませぬ。」
と言っては、次から次へと、高価な衣や首飾りをつけ、よその命(ミコト)や姫達に見せびらかしていました。
命達はそんな大山姫のことを、あのような姫をめとったら、一生の不運だと言って、誰も大山姫を妃に迎えようとしませんでした。
そんなわけで大山姫は、四十の坂を越してしまいました。
咲耶姫は大山姫が不憫でならず、この上は神におすがりしなければと、朝に夕に、
「おば姫の心を安らかにしたまえ。」
と心をこめてお祈りしました。
するとある夜、咲耶姫の夢枕に、月の神が立たれ、「明、十五夜の夜、大山姫をともない、更級の数々の峰を越えていき高根(高い山)に出でよ。そこに大岩があるから、その上へ登って、四方(ヨモ)を眺めよ、その時私の姿が、段丘の田毎に映り、そのさやけさで、大山姫の心はおのずと、清らかになるであろう。」
と告げられました。
次の日咲耶姫は喜びいさんで
「おば姫さま、お屋敷に閉じこもってばかりおられては、体の為になりませぬ。今宵は満月、お月見でもいたしませぬか。」
と誘いました。
「そういえば、ここ何年となく、お月見などしなかったから、行ってみましょう」
大山姫は思いがけなく素直にいわれて、衣はどれを着ていこうか、髪飾りはこれに決めましょうなどと、いそいそ身支度をなされました。咲耶姫は大山姫と連れ立って、月の神のお告げ通り、更級の数々の峰を越えて、高根に登りました。
「なんと見事な大岩でしょう。」
と大山姫は、一つの大きな岩を目ざとく見つけられて指さされました。
「おば姫さま、あの大岩へ登りましょう。」
咲耶姫は、この大岩こそ、月の神のお告げの大岩に違いないと、大山姫を誘って、その大岩へよじ登り、二人して四方を眺めました。
四方の山々は黒く静まりかえっていましたが、遥か下の方には、段丘の田毎の水に月影が映っていました。
ふたりはしばし無言のまま、その景色にみとれていましたが、やがて大山姫がしずかに口をひらかれました。
「咲耶よ、田毎の月かげのさやけさ、まこと、この世のものとも思われませぬ。なにやら、私の心の中のけがれが、みんなあらい落とされていくようじゃ、これもみな、咲耶のおかげじゃ。」
と目に涙をうかべていわれました。
「もったいのうございます。わたくしこそ、なにやら月のひかりで、こころの奥まで清められたようでございます。」
咲耶姫は今こそ、自分のまごころが大山姫に通じたかと思うと嬉し涙にくれました。
するとその時、月を伏し拝んでいた大山姫が、
「わたしがもし、月の宮へのぼれたら、この国をお守りになっていらっしゃる諏訪の神建御名方命(カミタテミナカタノミコト)のような神になりたいのですが。」
といわれました。
「え!月の宮へ!何もそんな遠いところへ行かなくても、私のそばにいつまでもいてほしゅうございます。」
咲耶は思いもよらぬ大山姫のことばに、ただおろおろするばかりでした。
すると空の月の宮から、
「大山姫よ!この浮橋をわたって来なさい。わたしと、月の宮でくらそう。」
と、諏訪の神のよぶ声がしました。そしてその声とともに、数百条と思われる綱のような浮橋が、月の宮から大山姫の足元へかかりました。大山姫と咲耶姫はふしぎななりゆきに夢でもみているような心地がしました。
「諏訪の神、まこと、私のような物でも、この国の守り神となれましょうか。」
と大山姫は、月の宮を仰ぎながら叫びました。
すると再び月の宮から、
「そなたの美しい心こそ、月の宮びととしても、国の守り神としてもふさわしいのです。」
と諏訪の神の声がしました。
大山姫はその声に誘われたかのように、一本の浮橋へ、足をかけられますと、
「咲耶、さようなら、おまえのやさしい心は、いつまでも忘れません。」と叫ばれました。その時、妙なる楽の音が響き渡り、大山姫の姿は、満月の中へ、みるみる小さくなっていきました。
咲耶姫はその姿を見送りながら、声を限りに叫ばれました。
「おば姫はこの高根に、みにくい心を捨てられ生まれ変わられました。おば姫をいつまでも忘れぬようこの高根を、おばすて山と呼ばせていただきましょう。」
更級の里、おばすて山に伝わるお話です。
(千曲市 八幡)
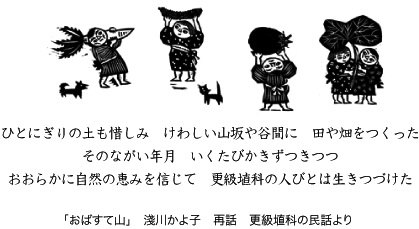
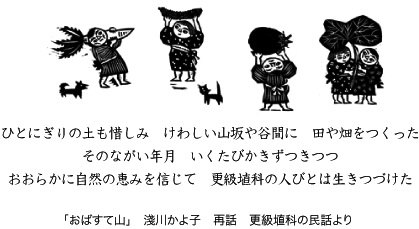
長野県千曲市は月の名所として知られ、多くの文人や俳人によってその美しさが詠われてきました。平安の昔から都人や旅人の「心のふるさと」であり、そして今も訪れる人にやすらぎを与えてくれます。
また、「おばすて山」にまつわる話として「楢山節考」などは有名ですが、この民話は残念ながらあまり知られていません。作り話ではありますが、このような話を親から子へと語り続けてきたこの土地の人々の温かい心根を誇りに思います。
木の花屋はこのふるさとの情景を守るとともに、この民話に表現された木の花姫の優しい心を大切に受け継いでいきたいと思います。
*ブランドという概念について
私たちは、「売れ“続ける”しくみをつくる」ことが、すなわち「ブランドつくりである」と考えています。
ですから、はるか古から人々の命をつなぎ、生活を豊かに支えてきた伝統食に敬意を表し、感謝し、その文化を次の時代に引き継ぐことを使命としています。

そのためには、社員が毎日誇りを持って働き、お客様の多様な人生の中でほんの一瞬でも「ホッとできる幸せ」を感じていただけるような商品を作ります。その対価としてお金をいただき、次にそのお金を使って野菜を購入することにより、農村や人々の生活を守ることができると信じています。そして、その自然の恵みと作り手の努力からうまれた野菜を使って、また心を込めて商品を作り続けます。
私たちは、冬には野山が凍るこの信州で、夏や秋に採れた旬の野菜を大切に保存する知恵を、すばらしいと感じています。食べきれない野菜を「塩に預けて感謝していただく」伝統の知恵とその本来の美味しさを伝え続けてまいります。
*木の花屋の商品について
木の花屋では、国産野菜を使用し、出来るだけ生産者様の顔が見える地元野菜を使用し、保存料や着色料は一切使わずに漬物やつくだに、そうざいなどをつくっています。味噌の大豆も国産です。
信州伝統野菜を使った商品は現在十数種類ございますが、まだまだ増やしてまいります。
旬の野菜を大切に保存する文化から生まれた、深い味わいの『漬け物・佃煮』。私たち、木の花屋は、商品を通じて、皆様のこころのふるさとになりたいと願っています。
木の花屋
ブランドマネージャー 宮城恵美子
経営理念
- 1伝統的食文化の継承と新たな食文化の創造により、お客様の心を真に豊かにできる会社を目指します。
- 2全ての社員が仕事を通じて価値観を高め、人間的に成長できる会社を目指します。
